生理休暇を「コアラ休暇」に。“保健師従業員”が働きやすい職場を目指して取組を支援
キーワードからキーワード別の記事一覧を見ることができます
タニタヘルスリンクでは、2022年に発足した「女性の活躍推進プロジェクト」が中心となり、女性の健康課題に関するさまざまな施策を進めています。保健師資格保持者としてプロジェクトをサポートする島田保子さんに、生理休暇の名称変更やフェムテック勉強会など具体的な取組の話を中心にうかがいました。
- 従業員アンケートを経て、生理休暇の名称変更。申請方法も見直した
- 月1回、女性従業員が集まって話す「ざっくばらん会」を開催
- フェムテック勉強会は、働く女性の視点で使用目的に合った商品を厳選

アンケートや「ざっくばらん会」で従業員のリアルな声を集める
女性の健康課題への取組は、女性活躍推進の一環になっているそうですね。
島田保子さん(以下、島田さん)2022年に「女性の活躍推進プロジェクト」が発足しました。弊社は従業員の男女比がほぼ同じです。そのような環境において、もっと女性が活躍できる環境を整えるために、女性従業員が女性の働きやすさやキャリア構築のために必要なことを話し合う場です。現在は、年代や部署、働き方や家庭環境のバランスを見ながら、会社が指名した9名の女性がメンバーになっています。
私は会社の「健康プロジェクト事務局」を代表して、サブメンバーのような形で参加しています。「健康プロジェクト事務局」とは、従業員への健康施策や健康経営の実施を目的として2009年に発足したCHO(Chief Health Officer)である社長直轄のチームで、責任者は副社長です。私は、保健師の資格を持ち、病院や保健所、保健センターのほか、介護支援専門員として介護に関する仕事に従事した経験があります。そのことから、健康に関するビジネス開発という通常業務のほかに、弊社の産業保健を担当し、健康プロジェクトメンバーとしても活動しています。女性の活躍と健康課題への取組は切り離せないことから、「女性の活躍推進プロジェクト」発足時から話し合いに加わっています。
「女性の活躍推進プロジェクト」をきっかけに始まった、女性の健康課題に関する取組を教えてください。
島田さん2022年に、生理休暇の名称を「コアラ休暇」に変更し、申請時の心理的負担を軽減しました。以前は生理休暇取得を事前申請する必要がありましたが、生理休暇は法律で権利として認められているのに事前の許可が必要な上に、男性の上長には申請しづらいという心理的取りづらさもあるのは変える必要があると考えました。それを社内で提案したら、必要な人が取得しやすいように名称変更をしてもいいのではないかという意見が出て、「女性の活躍推進プロジェクト」が中心となって、社内で名称を募集しました。
最終的に、応募の中から「コアラ休暇」が採用されました。コアラは、弊社の健康づくり応援キャラクターです。クマが男の子で、コアラが女の子。女性の休暇だから、コアラがいいね、と話し合いました。コアラはほとんど1日中寝て過ごすと動物ということから、1日中休みたいほどしんどい状態だという意味も込めています。申請も、オンラインの勤怠管理の画面から「コアラ休暇」を選択すれば申請できるようになりました。そのほか、加盟する健康保険組合のサービスを活用し、小児科・産婦人科・助産師に無料相談ができるようにしました。
生理休暇の名称変更を検討する過程で、女性の健康課題に関するアンケートも実施し、生理の不調だけでなく、PMSや更年期症状、不妊治療にも適用してほしいという意見がありました。アンケート結果は経営層にも共有しており、その時点で検討課題として認識されています。今年3月から、失効する年次有給休暇を積み立てる「積立年休」制度をスタートしたのですが、その適用範囲に含めることも検討しています。積立年休は、女性だけでなく全従業員の健康課題に対応できるように、運用しながら制度を整えていきたいと考えています。
アンケートは定期的に実施しているのですか?
島田さん年1回、健康経営や生活習慣に関するアンケートのほかに、女性の健康や活躍推進に関るアンケートも必要に応じて実施しています。健康課題だけでなく仕事との両立も含めたアンケート結果を参考にしながら、役員や産業医、従業員の代表、人事部門と連携して制度設計の検討などを進めています。
例えば、アンケートと「女性の活躍推進プロジェクト」での話し合いから、フレックスタイム制や時間有給制(時間単位での年次有給休暇取得)のほかに「一時外出制度」が導入されました。業務時間内に一時的に仕事を離れられる制度です。仕事中に一旦離席して病院に行くこともできるし、子どもの送迎や近親者の世話などをしてテレワークに戻るといった働き方もでき、仕事とプライベートの両立がしやすくなりました。女性従業員の声からできた制度ですが、子育て中の男性従業員の利用も多く、女性の意見を反映した取組が全従業員の働きやすさにつがなる好事例となりました。
また、アンケート以外に、「女性の活躍推進プロジェクト」主催で、定期的に「ざっくばらん会」が開催されています。これは、女性従業員が会議室に集まったりオンラインでつながったりして、なんでも話し合える会です。就業時間内の実施が認められており、毎回1時間の開催です。自由参加ですが、ほとんどの女性従業員が参加しています。ここでの話が制度設計の“元ネタ”になることも多いですね。直近では、キャリアビジョンについて話し合いました。正社員だけでなくパートなどさまざまな働き方の女性が参加していたので、雇用形態による悩みの違いも可視化されて、立場の違う人たちの考えを皆が共有できる、とても有意義な機会でした。

フェムテックや子宮がん検診に対する正しい知識を保健師が伝える
タニタヘルスリンクでは、「女性の活躍推進プロジェクト」発足以前から女性の健康課題に着目してきたと聞きました。
島田さん近年、企業が女性の健康課題に着目し始めたと感じていますが、弊社では2013年頃から取り組んでいます。2009年の「健康プロジェクト事務局」発足のきっかけはメタボリックシンドローム対策でしたから、プロジェクトの内容もウオーキングや体組成計での測定、食事の改善などが中心でした。けれど、女性の健康課題の改善は、それだけでは実現しません。女性のプレゼンティーズム(心身の不調を抱えながら業務を行っている状態)を改善しパフォーマンスを上げるためには、全従業員向けの取組とは違ったアプローチが必要だと、私から提案しました。
最初にどのような取組をしたのでしょうか?
島田さんまず、女性従業員向けと管理職向けの2種類の女性の健康課題に関するセミナーを開催しました。弊社はさまざまな健康サービスを提供する企業で、サービス開発には社内の取組から得られた成果を活用しています。セミナーを開催した当時は、一般的には女性のからだについて、男性はもちろん女性が職場で話すということはあまりありませんでした。しかし、保健師として参加したいくつかの学会で女性の健康課題が取り上げられ始めていたので、いずれは社会的に注目されるようになると感じていました。セミナー開催にあたり、今後、女性の健康課題が社会的にフォーカスされていく可能性が高いと伝えたら、管理職も積極的に参加してくれました。
現在もセミナーは積極的に開催しているそうですね。
島田さん弊社は理学療法士や管理栄養士など、専門資格を持った従業員が多くいますから、その者たちが講師となってセミナーを開催しています。理学療法士の骨盤底筋体操や管理栄養士の栄養セミナーなど、社内でいろいろできます。
女性の健康課題については、昨年、フェムテック商品の勉強会をしました。「女性の活躍推進プロジェクト」の会議でフェムテックが議題になったとき、メンバーの一部から、興味はあるけれど使い心地が分からないと買いづらいという意見が出て、社内で勉強会をすることになりました。勉強会ではプロジェクトメンバーが興味のあるものを経費で購入し、参加者が実物を見た後、お試し用に持ち帰れるようにしました。アイテムは購入前に一度リストアップしてもらい、私がチェックしています。フェムテック商品の中にはお薦めできるものとそうでないものがありますから、保健師の目線で商品を絞りました。
また、勉強会の講義構成は任せてもらい、商品を紹介するだけでなく、改めて生理を知る機会としました。例えば、月経カップなどフェムテック商品を紹介しながら経血の量の話もして、あまりにも多いようだったら病気が見つかる可能性があるので婦人科を受診するように伝えました。他のアイテムも、正しい使い方と一緒に紹介しています。意外に反響があったのが、生理用品と尿漏れパッドの比較でした。購入が恥ずかしいという理由で、尿漏れパッドの代わりに大きめの生理用品で代用する方も多いんですね。けれど、吸収量が違います。勉強会当日、水を使ってその違いなどを目で見て比較しながら、「これだけ違いますから、きちんと尿漏れパッドを使ったほうがいいですよ」と伝えました。出産後、一時的に尿漏れすることもあるので講義内容に含めたのですが、自身の母親と共有してくれた方も複数名いました。
弊社のセミナーは参加率がとても高く、オンライン動画でも視聴もできるので、同じセミナーを繰り返すことはほとんどありませんが、フェムテックの勉強会をはじめとした体験型セミナーはとても反響が高かったことから、継続して開催したいと考えています。
セミナーでは、婦人科の受診も勧めたのですね。
島田さんはい。これは、産業保健師の立場で力を入れていることでもあります。定期健康診断の結果で再検査や精密検査が必要となった従業員は、産業医と連携して、私が個別面談したうえで受診を勧めています。健診時の婦人科検診で異常が見つかれば面談で受診を勧めますが、生理時の不調やPMSなど、数値だけで見つけづらいものもあります。女性の健康課題はとても複雑ですから、婦人科のかかりつけ医を持ってほしいと思い、啓発しています。
今後、力を入れたい女性の健康課題への取組はありますか?
島田さん今は特に、がん検診を知識と共にしっかりと啓発していきたいですね。弊社の定期健診は受診率100%で、がん検診も、対象となる年齢の方はほぼ受けています。また、定期健康診断とあわせて、乳がん検診と子宮頸がん検診が受けられるようにしています。検診受診時及び再検査や精密検査なども就業時間内で受診することが認められていますので、積極的に受診してほしいと思っています。受診をきっかけにヘルスリテラシーが向上して、婦人科のかかりつけ医を持つことにつながってほしいと考えています。

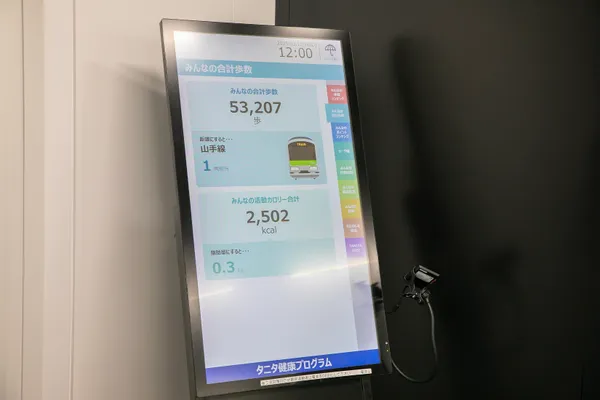
事業ヘルスケアサービス事業
従業員数/74名 女性従業員数/44名(2025年3月末時点)
(※内容は2025年3月取材時点のものです)